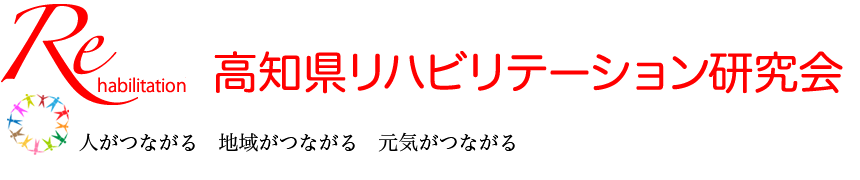本年度大会情報
- 第57回 高知県リハビリテーション研究大会 介護人材不足と利用者確保難にどう向き合うか ~高知県幡多地域からの発信~(掲載日:2025年10月11日)
-
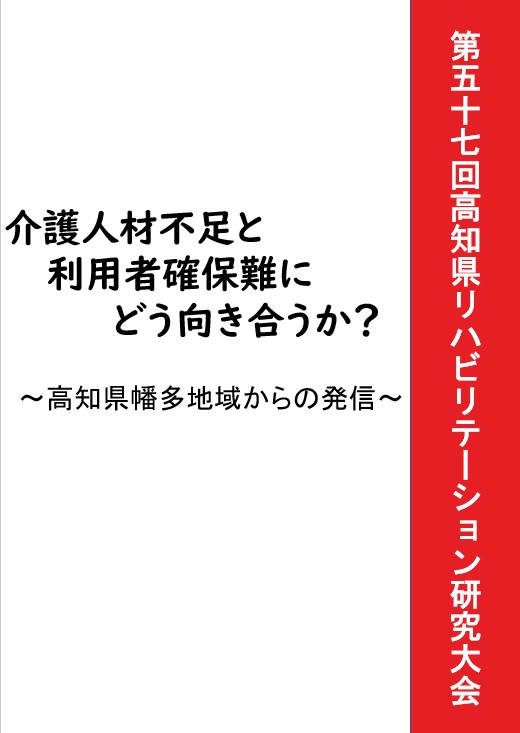
~開催趣旨~
いま日本は「2025年問題」「2040年問題」という大きな転換点に直面しています。2025年には団塊の世代がすべて後期高齢者となり、医療・介護需要が急増します。総務省の推計では75歳以上人口は約2,179万人に達し、医療給付費は約48兆円、介護給付費は約15兆円規模に拡大する見通しです。さらに2040年には団塊ジュニアが高齢者となり、全国の高齢化率は35%を超え、医療・介護費用は現在の1.4〜1.7倍に膨らむとされています。
必要とされる介護人材は2026年度で約240万人、2040年度で約272万人と推計されますが、現状からみて25万人から57万人の不足が見込まれています。高知県においても2026年度には約411人、2040年度には約1,984人の介護人材が不足するとされ、特に幡多地域では過疎・高齢化が顕著であり、人材の確保と育成は喫緊の課題です。
一方で、高知県全体では人口減少が加速しており、自然減が社会減を上回っています。高齢者人口の減少は介護サービス利用者数の減少にも直結し、施設の空き定員や待機者減少が顕在化しています。つまり、人材不足と利用者減少という二つの相反する課題に同時に向き合う必要があります。
このような状況の中、地域の持続可能性を守るためには、予防・医療・福祉・行政・住民が一体となり、それぞれの役割を果たしながら連携していくことが不可欠です。幡多地域からの発信として、限られた資源を有効に活用し、高齢者にとっても事業所にとっても安心できる仕組みを構築することが求められています。
介護人材の確保と利用者の安定的な支援を両立させながら、地域に根差した持続可能なシステムづくりを探り、次世代へとつなげていくことが、私たちの使命です。
◆開催日 令和7(2025)年11月9日(日)13:00~16:30
◆会場 四万十市総合文化センター(しまんとぴあ) 大会議室1&2
【オンライン(ZOOM)併用開催♪】(住所:四万十市右山五月町7番7号)
◆定員 オンライン:95名、会場:60名(先着順)
◆主催 高知県リハビリテーション研究会
~高知県に地域リハビリテーション※の理念を普及させる~
・大 会 長 宮本 寛 (高知県リハビリテーション研究会 会長)
・実行委員長 田中きよむ(高知県リハビリテーション研究会 理事)
◆後援 高知県
◆参加費 会員・非会員問わず 無料!!
◆参加方法 下記のURLまたは、右の二次元コードからお申込み下さい。 https://rihaken4.wixsite.com/57taikai
~ URL及び二次元コードからの申込みが難しい場合 ~
別紙 参加申込書により、11月4日(木)までに、事務局あてにFAX又はEメールでお申し込みください。
【日程】
12:40~ 会場受付・ZOOM入室可能
13:00~13:10 開会
開会挨拶 宮本 寛 (第57回高知県リハビリテーション研究大会長)
13:10~14:00 基調講演「介護人材不足の背景・状況と今後の方向」
講師:田中 きよむ(高知県立大学社会福祉学部教授、
(休憩) 高知県リハビリテーション研究会理事)
14:10~16:30 パネルディスカッション
介護人材不足と利用者確保難とどう向き合うか
~保健・医療・福祉・行政・住民のスクラムをめざして~
○パネラー(50音順)
・荒川泰士 氏(高知県ホームヘルパー連絡協議会会長)
・芝岡美枝(高知県幡多福祉保健所地域支援室長)
・西本久美香(NPO法人「ふくしねっとCoCoてらす」事務局長)
・溝渕敏水(医療法人聖真会渭南病院院長)
・山本博昭(四万十市社会福祉協議会局長)
○コーディネーター
・田中きよむ(高知県立大学社会福祉学部教授、高知県リハビリテーション研究 会理事)
16:30 閉会 閉会挨拶 田中きよむ(第57回高知県リハビリテーション研究大会実行委員長)
※ 質疑応答の時間を設ける予定ですが、オンライン参加の皆様はZOOMのチャット機能でのみご質問を受けさせていただきますので、よろしくお願いします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※≪地域リハビリテーションとは≫
障害のある子供や成人・高齢者とその家族が、住み慣れたところで、一生安全に、その人らしくいきいきとした生活ができるよう、保健 ・医療・福祉・介護及び地域住民を含め生活にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行なう活動のすべてを言う。(「日本リハビリテーション病院・施設協会」の定義より)